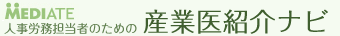紫外線と健康

夏至前後の今の時期は、一年のうちで紫外線が最も強くなる季節です。
紫外線にはカルシウム代謝に不可欠なビタミンDの合成といった健康維持に大切な役割もありますが、紫外線を過度に浴びることによって、日焼けなどの急性障害だけなく、皮膚のシワやシミ、皮膚がんや白内障といった慢性の健康障害が起こると言われています。このため、紫外線を過度に浴びない様、対策を行っていくことが必要です。
紫外線とは
太陽の光には、目に見える可視光線のほかに、目に見えない赤外線や紫外線が含まれています。
紫外線とは地表に届く光の中で、最も波長の短いものです。
紫外線は波長の領域とそれに伴う性質によって、A、B、Cに分けられ、それぞれ以下の様な性質を持ちます。
UV-A
大気圏でほとんど吸収されずに地上に到達する。UV-Bよりも健康への影響は少ないものの、長時間浴びた場合は健康への影響がある。
UV-B
大部分は大気層で吸収され地表に到達するのは一部だが、UV-Aよりもエネルギーが強く、日焼けや皮膚がん、眼等の健康障害を引き起こす。
UV-C
大部分は大気層で吸収され地表に到達しないが、最もエネルギーが強い紫外線。殺菌灯にも利用されている。
紫外線の強さは、季節や時刻、天候、オゾン量によって大きく変化します
- 日本では1年の内、春から初秋にかけてが強く、4 ~ 9月の紫外線照射量は、年間照射量のうちの70~80%を占める。
- 1日の中では正午前後、太陽が最も高くなる時間(南中時)に紫外線は最も強くなる。
夏の午前10時~午後2時に1日の照射量の約70%、冬の同じ時間帯では1日の照射量の内80~85%を占める。 - 緯度が低くなる(南にいく)程、強くなる。
- 薄い雲ではUV-Bはほとんど遮られず、80~90%が透過してしまう。
- 標高が高いほど、より強い紫外線を浴びることになる。
- 地表面の性質によっても影響が異なり、新雪や砂浜、海などの水面では反射率が高く、スキーや海水浴のときには強い日焼けをしやすくなる。
紫外線の健康への影響
急性障害
紫外線による急性の影響としては「日焼け」があります。
サンバーン
日光に浴びて数時間で起こり、炎症で皮膚が真っ赤になって痛みを伴う。
日光にあたってから8~24時間でピークとなり、2~3日で症状が治まる。
サンタン
数日後にメラニン色素が増えることで皮膚が黒っぽくなる。
皮膚が黒っぽくなったあと数週間から数か月続く。
日焼けの影響は個人差が大きく、人種によっても異なります。
白人はサンバーンを起こしやすいですが、サンタンを生じにくく、日本人の様な東洋人は、サンバーンを起こした後、その後多少のサンタンを起こし黒くなるタイプが多いと言われています。
この他、「雪目」として知られる紫外線角膜炎や、一時的な免疫機能の低下を起こすとも言われています。
慢性障害
光老化
紫外線を長年浴び続けると、皮膚のシワやシミ、老人班、腫瘍(良性・悪性)の発生に影響を与える。
目の病気の発症
白内障や翼状片(眼球結膜(白目)が翼状に角膜(黒目)に侵入する線維性の増殖組織で、瞳孔近くまで進展すると視力障害をきたす)といった目の病気の発症に影響を与える。
紫外線による健康影響を減らすために

紫外線を過度に浴びない様、紫外線が強い今の時期は特に注意して対策をしましょう。
対策は以下の通りです。
① 日焼け止めを上手に使う
液体や乳液、クリーム、スプレー等様々な形態のものがあり、紫外線防止剤として紫外線吸収剤と紫外線散乱剤が使われている。
紫外線吸収剤
塗った際に皮膚が白く見えないものの、まれにアレルギー反応をおこす人がいる。
紫外線散乱剤
少々白く見えるがアレルギーをおこすことがほとんどない。皮膚の敏感な方、アレルギーが心配な方は、は紫外線散乱剤のみを含んでいるものを選ぶと安心
日焼け止めの表示にある、SPF はUV-Bを防ぐ指数(2~50+)、PAは UV-A(+~++++)を防ぐ指標となっている。
② 紫外線が強い正午前後の時間帯の外出を避ける
曇りの日も紫外線量は強いため注意する
③ 日陰を利用
なるべく直接日光に当たらない様にする
④ 日傘や帽子、衣服で紫外線をカットする
つば広の防止や色の濃い衣服はより紫外線を避けるのに効果的
⑤ サングラスをかける
目の保護のために紫外線カットのサングラスを利用する
株式会社メディエイト 保健師 小河原 明子