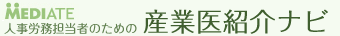アルコールと依存

アルコール健康障害対策基本法では、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、11月10日~16日までをアルコール関連問題啓発週間と定めています。
お酒は私たちの生活を豊かにしてくれる一方で、不適切な飲酒は心身の健康障害を引き起こすだけでなく、飲酒運転、暴力などの社会的問題を引き起こすこともあります。
また、アルコールには依存性があり、依存症に至ると仕事や家族関係においても様々な問題を引き起こします。厚生労働省の推計では、日本でも約100万人(約100人に1人)のアルコール依存症患者が存在し、その予備軍は数百万人に上るとも言われています。
今回はアルコールと依存についてお伝え致します。
アルコール依存症とは
アルコールが好きでよく飲むという場合でも、状況や体調によって飲む量を減らしたり、飲むことを中止することができる場合は依存ではありません。「お酒好き」と「アルコール依存症」との違いは「自分の意思で飲酒のコントロールができるかどうか」という点にあります。
不適切な飲酒を続けることで、自分の意思では「飲む量」や「飲む時間」、「飲む状況」といった飲酒のコントロールができなくなった状態がアルコール依存症です。
アルコール依存症では、健康状態や仕事、家庭といった社会生活に様々な問題が生じるようになります。お酒をやめたい、やめるべきだと思っても、飲むことをやめることができない状態、これが依存症の状態です。
アルコール依存症の症状と進み方
①「耐性」の形成
ストレス発散やリラックスのために飲酒していても、それが習慣化し飲む量が増えてくると「耐性」が形成される。
![]()
②「精神依存」が生じる
「耐性」が形成され、今までと同じ量を飲んでもアルコールが効きにくくなり、徐々に飲む量や回数が増えていく。
そして「お酒が欲しくなる、お酒を飲まないと落ち着かない」といった
「精神依存」が生じる。
まだ大きな問題は起こらず社会生活維持される。
![]()
③「身体依存」が現れる
多量飲酒を習慣的に続けていくと現れる。
お酒が切れると様々な症状が出現する。この症状は離脱症状と呼ばれ、お酒を止めたり飲む量を減らすと、不眠・発汗・動悸・手の震え・不安・いらいら感が現れ、症状が重くなると幻覚やけいれん発作を起こす。
![]()
④社会生活維持困難
飲酒すると離脱症状が治まるため、更にお酒を飲んでしまうという悪循環に陥る。この段階になると、遅刻や欠勤、パフォーマンス低下等仕事にも影響が出てきたり、家族関係が悪化したり、アルコール起因の病気が発症するなどして、社会生活が維持できなくなる。
アルコール依存症の診断
アルコール依存症の診断は、主に以下の「ICD-10」の診断基準が使われています。
※ 過去1年間に以下の6項目のうち3項目以上を同時に1か月以上経験するか、繰り返した場合に診断されます。
| ① | 激しい飲酒渇望 | 飲酒したいという強い欲望あるいは切迫感 |
| ② | 飲酒コントロールの喪失 | 飲酒行動(開始、終了、量の調節)を制御することが困難 |
| ③ | 離脱症状 | 断酒や節酒による離脱症状の出現、離脱症状の回復・軽減のために飲酒する |
| ④ | 耐性 | 今までの飲酒量では酔わなくなり、更に飲酒量が増える |
| ⑤ | 飲酒中心の生活 | 飲酒のために本来の生活を犠牲にする、アルコールの影響からの回復に時間がかかる |
| ⑥ | 問題があるにも関わらず飲酒を続ける | 心身に問題が生じているにもかかわらず飲酒を続ける |
アルコール依存症への対応

アルコール依存症は、早い段階で気づき、治療を開始することが重要です。習慣的に飲酒される方や飲酒量の多い方で依存症が心配な方は、かかりつけ医や各自治体の相談窓口、専門の治療が可能な医療機関に相談しましょう。
なお、依存症のリスクがあるかどうかをチェックできるツールがWEB上でも公開されています。依存症が心配な方は、まずはそのようなツールを利用してリスクを確認することもできます。
無理のない飲酒習慣を
毎日の飲酒量が3合(ビール500ml缶3本)以上になると、依存症のリスクが高まると言われています。1日の適正飲酒量は1合程度(ビール500ml缶1本)と言われていますので、この量を目安に、休肝日を設けながら、心身に影響の出ない範囲でお酒を楽しみましょう。
株式会社メディエイト 保健師 小河原 明子