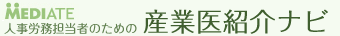ラインケアでメンタルヘルス不調を予防しましょう

異動や昇進、入社などで環境の変化が大きかった4月が終わり、ゴールデンウイークのお休みが明けるこの時期は、5月病の様な心身の不調が現れやすい時期です。
このような心身の不調に対しては、不調の早期発見・対応が重要です。
今回は「ラインケア」の視点から、この時期の心身の不調へ対応していくポイントについてお伝え致します。
ラインケアとは
職場におけるメンタルヘルスケアでは、4つのケアが 継続的かつ計画的に行われることが重要とされている。
① セルフケア
② ラインケア
部長や課長といった管理監督者によって行われるケアです。
管理監督者には部下である従業員の健康に配慮する役割も求められています。このため、部下の心身の健康状態を把握したうえで、必要なケアを行っていく必要があります。
③ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
④ 事業場外資源によるケア
「いつもと違う」様子に気づくことがポイント
部下のメンタルヘルスの状態を把握する上でポイントとなるのが、「いつもと違う」部下の様子に気付くことです。
早く気付けるようにするためには、日ごろから部下に関心を持って接し、部下の行動パターンや人間関係などに意識を向けることが必要です。
「いつもと違う」部下の様子に気づくポイント
勤怠
・遅刻、早退、欠勤が増える
・休みの連絡がない(無断欠勤がある)
・残業、休日出勤が不釣合いに増える
仕事
・仕事の能率が悪くなる。
・思考力・判断力が低下する
・業務の結果がなかなかでてこない
・報告や相談、職場での会話がなくなる(あるいは多弁になる)
行動
・表情に活気がなく、動作にも元気がない(あるいはその逆)
・不自然な言動が目立つ
・ミスや事故が目立つ
・服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする
「いつもと違う」ことに気づいたら、産業医や産業保健スタッフと連携し対応を

部下の「いつもと違う」様子に気づいたら、その背後に病気が隠れているかを確認する必要があります。病気の可能性があるかどうかについては管理監督者が判断することはできませんので、産業医や病院の医師による判断が必要です。
- 管理監督者は部下の話を聞き、本人に産業医への相談を促す。
- 部下への対応方法を管理監督者自身が産業医へ相談する。
などといった対応が必要となります。
産業医以外に保健師や心理相談担当者、産業カウンセラーなどの産業保健スタッフが事業場内にいる場合は、連携して対応していきましょう。
日頃から不調者が出た場合に産業医や産業保健スタッフへつないでいく仕組みを作っておくことも、早期対応を行っていく上でのポイントとなります。
日頃から部下が相談しやすい環境を作りましょう
メンタルヘルスの不調を早期発見するためには、部下が自発的に不調を感じていることや困っていることを管理監督者へ相談できる環境や雰囲気を整えておくことも大切です。
そのためには、日頃から部下の話をじっくり聞く「傾聴」を行っていくことが重要です。「傾聴」することで部下との良好な関係が構築され、部下が問題や不調を抱えている場合に、管理監督者への相談につながりやすくなります。
傾聴を行う際のポイント
相手を受け止める
→ 相手に対して関心を持っていることを、表情や態度で相手に伝える
相手の立場に立つ
→ 「もしも自分が相手と同じ立場に置かれていたら」ということを意識して話を聴く
個人情報への配慮も大切に
部下からの相談を受ける場合に注意が必要なことが「個人情報への配慮」です。
法令によって、情報の収集や管理、使用に際しては、本人の同意を得ることが原則となっており、管理監督者は部下の健康情報を含む個人情報を保護し、部下の意思の尊重に努める必要があります。
このため、部下への声掛けや相談を受ける場合には、この個人情報への配慮を忘れず行うようにしましょう。
株式会社メディエイト 保健師 小河原 明子